ポニポニピープル Dialogue 005 村瀬孝生
(3/7)包摂しているのはどっち
菊地玄摩 村瀬さんのポニポニ関連企画への出演は、「ポニポニ文化会議」、「湯リイカ」、「ケアを手放す夜」、「にんげんフェスティバル」など、5、6回になると思います。
村瀬孝生 そうですね。回数はっきりとは覚えてないですけど、どれがポニポニでどれが山内さん単独か、僕がわかっていないのかも知れませんけど。東京で伊藤亜紗さんとご一緒した時も「ポニポニ文化会議」でしたから、それくらいの回数になると思います。
菊地玄摩 その都度、山内さんが興味のポイントを伝えてくれるんじゃないかなと思います。
村瀬孝生 そうですね。「にんげんフェスティバル」の時に、大牟田駅前のビルでトークイベントを二ノ坂先生とさせていただいたり、打ち上げの時にポニポニのメンバーの人たちと接したときに、やっぱり面白いことしてると感じましたね。それってロジカルにこういうことだから面白いんですねという理解の領域じゃなくて、大牟田のあそこに身を置くと、ますます体感的に「やっぱり面白いことしてるんだ」という実感がありましたね。

菊地玄摩 山内さんが村瀬さんを面白がって「よりあい」までお話に来て、村瀬さんも大牟田に行けば面白いと感じられるという、良い関係ですね。
村瀬孝生 僕は「よりあい」をそろそろ引退だということをずっと言っていて。実際自分の今までの積み上げの中から、年齢が上がるというのは社会から離れることだと思っていてですね。「社会から離れられる老人」になりたいと思っているわけですよ。
菊地玄摩 そうなんですか。
村瀬孝生 そうです。社会から離れられる老人になっていこうと思いますけど、ポニポニや山内さんとの関係は続けていきたいですね。
菊地玄摩 社会から離れられるというのはどういうことでしょう?
村瀬孝生
このへんはね、今、奇奇怪怪な状況になっているというか。「よりあい」で活動していると、認知症やぼけがあることによって、具体的な困り事が起こるわけですよね。自分のバッグじゃないのに自分のバッグだと言ってみたり、デイサービスのスプーンを自分の物だと思ってバッグに入れちゃったり、自分の居場所じゃないと思っていなくなってしまう。
そういう風に、今まで生きてきた社会の中の共通言語を失って、本当に生き物に帰っていく、そういう人たちをいかにこの社会で包摂していくかということに取り組んできたんですよ。ですが、「包摂する」という考え方自体に誤りがあったと最近気づいてですね。
菊地玄摩 そうなんですか。
村瀬孝生
人間社会のほうが、閉じこもった人間だけで完結する小さな社会であって。実は、それを包摂している「世界」のほうにお年寄りは行くんだ、ということに気づいたんですよね。
だから実は、深い老いとかぼけの世界が、「世界」として人間社会を包摂しているのに、我々の小さな「社会」が包摂してやろうという風に考えていたことが大きな間違いだったんだなと、最近気づかされました。
僕は、小さな自己完結的な人間社会を包摂している「世界」の方に行こうということなんです。今それを人間社会がさせないようにしていて、そっちに行くとバカになっちゃうとか言われるし、僕らも孤立する。孤立を防ぐんだと言っていたのは、小さな人間社会の中だけの話であって、私はこの社会を包摂する側の方にいける老人になりたい。しかし、今の社会ではそうはいかないんです。そっちは非人間的であり、気の毒な人間になっちゃうので。一生懸命治療したり訓練したり、財政的な理由から歳をとらないように頑張りましょうという社会になっていっているので、この社会からいかに距離をとるか。そういう場所が全くないわけですよね、今は。そっちのルート探しをしたい、そっちに移りたいです。
菊地玄摩 山内さんはもしかして「世界側」に片足突っ込んじゃってるんでしょうか。ぼけないままに。
村瀬孝生 いや、どうなんでしょう。その「世界」が存在していることを知っている、ということじゃないですかね。今の社会の中で、経済的に生きていこうとすると離れられないんですよ。強力な経済的合理性の磁場で、がんじがらめになっている。そこから離れてしまうのは、深い老い、認知症やぼけを抱えた人たちなんですよ。我々の自己完結的な社会から見ると、不幸な人たちなんだけど、実は当事者はそうは思ってないだろうなと。それは、実際今まで支援していく中で感じてきて、その理由が僕なりにわかってきたというか。
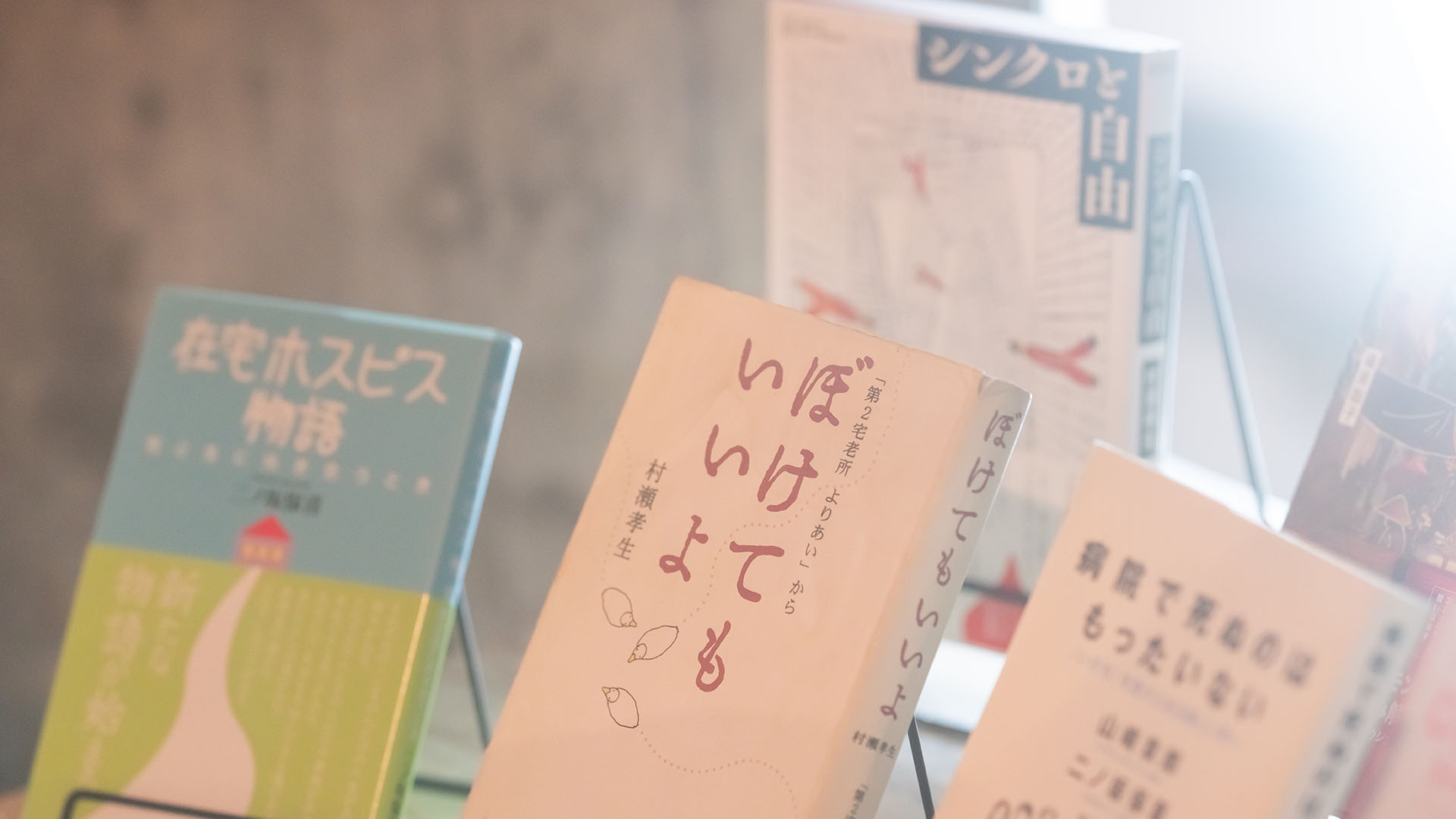
菊地玄摩 なるほど。村瀬さんも最近そう思われるようになったんですね。その認識の移行は、どういう風に起こるものなんでしょう?
村瀬孝生
そうですね。僕らには元々、人間が作ってきた社会の規範に沿えなくなって離れていくお年寄りたちに、悲しみがあったんですよね。悲しみの正体は、帰属していた集団から居場所を失っていく悲しみでもあったし、社会側の喪失感でもあった。「老いは喪失の文化」と老人福祉領域で教えていましたからね。僕もそういうものの見かたをしていたけど、それはあまりに僕らの論理であって。日常生活の中でも万策尽きたときに新しい地平が見えてくるのと同じで、老いが深まって、今までの規範に沿っていた自分が沿えなくなって、そこから離れざるを得なくなった時に、次の地平が待っていただけなんだ思いました。
僕は現場に入って37、8年目になるんですけど、ここまで感じてきたことを、この歳になって言葉にし始めたんじゃないかと思います。これまでは言葉にするよりも「今日どうする!?」だったわけです。「今日の夜どうしても看れないんです」などの事情に、毎日振り回されていたので。感じていたことはたくさんあったんでしょうけど、言語化する暇もなかったというのがあります。
僕の場合は、時々エッセイであったり連載での形で文書にすることが、若いときから今までずっと途切れることなく続いてる。いま若手にバトンタッチをして現場から離れるという状況と、母の介護に集中するというようなタイミングで60歳になって、いろんなことの言語化が起こっている感じがします。